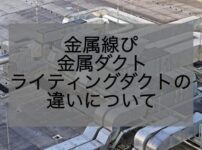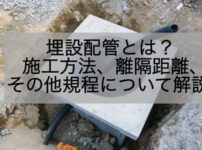新着記事
【疑問】金属線ぴ(モール)、金属ダクト、ライティングダクトの違いと使い分けを内線規程をもとに解説
金属線ぴと金属ダクトとライティングダクトは、いずれも電路を収納したり、電気の通り道になるようなもので似たようなイメージですよね。 形状としては全て細長い箱状で、最初は用途や使い分けもイマイチわからないかと思います。 金属線ぴと金属線ぴの明確な違いは幅が5cm以下か5cm超過で区別できます。 ライティングダクトについては、導体が一体化しているので上記二つとは明確に違います。 いずれも内線規程にしっかり規定されていますので、現場での使い分けも含めて詳しく説明していきます。 金属線ぴ 金属線ぴはメタルモールとレ ...
【電気配管】地中埋設配管とは?施工方法、離隔距離、その他規程について解説【電線管】
地中埋設配管とは? 電線を通すための電線管を地中に埋設する工法です。 都市部の道路などでは景観の向上という観点から、送電線の地中化が進んでいます。 建物の敷地内においては、受電ケーブルの引き込みや、建屋との渡りケーブルなど敷地内に架空電線を引き回さなくて済むメリットがあります。 景観の向上や電線の引き直しの施工性の向上というメリットの反面、電線管自体の改修は大掛かりになることや、雨水の侵入の防止が困難なので電線の絶縁という面でデメリットがあります。 地中電線路はケーブルのみ 内線規程、電気設備技術基準にお ...
今回は、電気工事に使用する電線管のうち、金属管について詳しく解説します。 サイズなどの教科書では学べない豆知識も紹介しますので是非ご覧ください! 金属管工事(金属管配線)とは 金属管工事とは、文字の通り金属の管となりますが、基本的には電線を保護するために使用される電線管の一種です。 内線規程では「金属管配線」、電気設備技術基準では「金属管工事」という名称で規程されています。 この規程は、管の内部が絶縁電線の場合に適用されるもので、ケーブルの場合はケーブル工事に該当します。 現在の電気工事の配線は、ほとんど ...
【疑問】木造住宅において金属管工事(電線管)を施工してもよいのか?電技、内線規程を紐解いてみる
住宅などの木造建築に対し、金属管いわゆる鉄管を使った電気工事を施工してよいかについて話題になることありますよね。 「木造に金属管は禁止!」というのは規程上どうなのでしょうか? 結論としては、基本的に問題ないが一部はNGとなります。 今回は、木造建築に対する金属管施工について電技や内線規程を紐解きながら解説していきます。 「木造に金属管禁止」といわれるようになった根拠規程 木造に金属管がNGというとよく言われることがありますが、確かに電技や内戦規程にそのような規程がありますので下に紹介します。 電気設備技術 ...
【疑問】漏電遮断機(ELB)はアースがなくても動作する?家電のアースの意味について解説
冷蔵庫や電子レンジ、洗濯機など、漏電した場合に危険が伴う家電にはアース線がついています。 コンセントプラグからちょろっと出ている緑色の線ですね。 このアース線はコンセントのアースターミナルに接続します。 家電が置かれる場所のコンセントは設計段階でしっかりとアースターミナル付きのものになっています。 あまり意識しないとアース線を処理しないということもあるかもしれません。 その場合どうなるのでしょう。 なんとなく感電を防止するために設置される漏電遮断器が動作しないのではないかと考えそうですよね。 結論としては ...